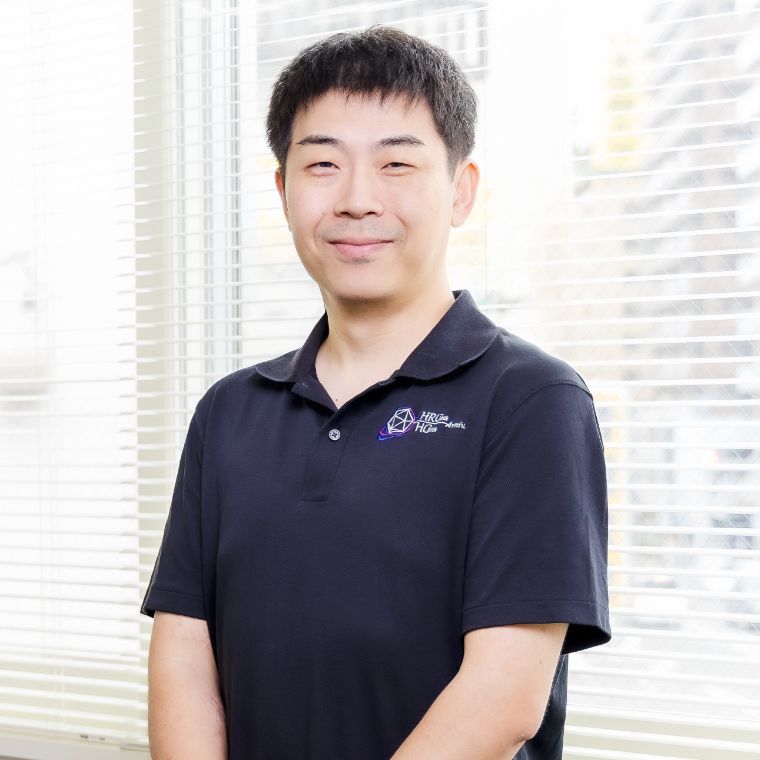Members
社員インタビュー

社会インフラの“未踏領域”に挑む。― 鉄道構造物と真剣に向き合う若手技師の、挑戦と探究の日々 ―
H.M.鉄道構造技術部 技師(東京事務所)
Theme 01 HRC研究所に入社した経緯
鉄道インフラを支える実感と、自由な働き方

入社を決めた理由は二つあります。一つは、業務の対応範囲が全国に及び、多様なプロジェクトに関われること。もう一つは、出社と在宅勤務を組み合わせた柔軟な働き方ができることです。自分の生活にフィットする環境で、幅広い仕事に携われる点に強く惹かれました。
もともと、土木構造物の中でも人の生活と密接につながるインフラに興味があり、“移動”を支える鉄道構造物の設計ができることにも大きな魅力を感じました。現在は、新幹線などの橋梁設計に加え、有ヒンジPC橋の長期たわみ解析にも取り組んでいます。特に後者は、高材齢のコンクリート橋を対象に載荷荷重による変形を解析する、これまであまり前例のない分野。未知の領域に挑む難しさと面白さがあり、大きなやりがいを感じています。
Theme 02 成長を実感した仕事
議論ができる風土が、知見と技術を深めてくれる
当社で特に魅力に感じているのは、風通しの良い社風です。同じ業務に携わっていない社員でも、気軽に相談や議論に応じてくれる環境が整っており、分野を越えた知識の吸収や視野の広がりにつながっています。多くの専門家が近くにいるからこそ、成長のスピードも早まっていると感じます。
中でも印象に残っているのは、超高材齢のコンクリート橋の載荷荷重による橋の変形解析です。直感的なイメージと大きく異なる結果が出たため、その解析結果が妥当かどうか、チーム内でも見解が分かれました。そこで社内の別チームに助言を仰ぎ、より深い専門知見と照らし合わせながら自身の考えを整理・強化。発注者との打ち合わせでも、論理的に説明し、理解を得ることができました。多様な視点と議論の機会が、自分の技術を支えてくれています。

苦手だった構造力学が、
今の仕事の核になっている
学生時代は水工学に強い関心があり、自分の得意分野だと感じていました。ところが実際に就職してからは、水工学よりも構造力学やコンクリート材料の知識が求められる業務が中心となっています。これらの科目には苦手意識があり、当時はあまり力を入れて勉強していませんでしたが、今では「もっと学んでおけばよかった」と痛感しています。
社会人になると、学生時代に学んだ基礎が実務で生きる場面が多くあります。とりわけ設計業務では、理論と現実の間を埋めるための知識が不可欠です。現在は日々の業務を通じて苦手を克服しながら、少しずつ理解を深めている段階です。学生の頃の自分に「苦手なものこそ、未来の武器になる」と伝えたい気持ちです。